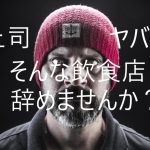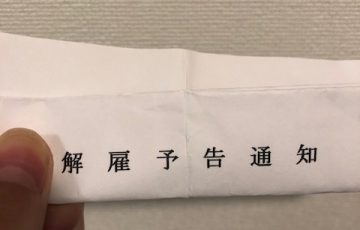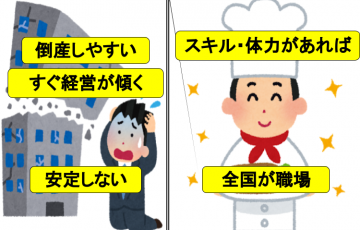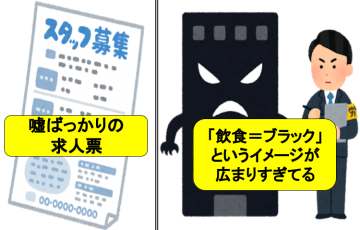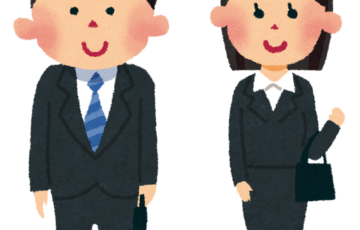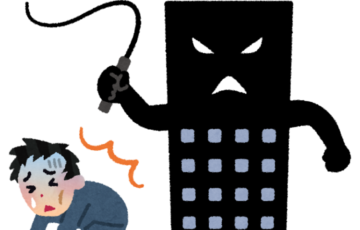- 【辞めたい】飲食店で社員がバックレるのも手段【体験談を聞いてきた】 - 2025年3月6日
- 飲食に就職すること検討してる人向け まとめ - 2024年7月27日
- ブラック企業の特徴や辞め方・抜け出し方についてのまとめ - 2024年7月25日
女性の方へ向けた内容となっている。
今付き合ってる彼氏が飲食店勤務、もしくは結婚した夫が飲食店の正社員の場合、このまま一緒に過ごすと孤独やストレスを抱え込むことになる可能性がかなり高い。なぜなら、飲食店の従業員は労働時間が長く、休日も少ないため一緒に過ごせる時間がとても少ないからだ。
飲食店勤務の男性と末永く二人で暮らそうと誓いあっても、その他、何かと不都合が頻繁に起こるだろう。
飲食店に勤務する人を結婚相手に選ぶとどんなことが待っているのか?
元飲食店勤務の俺が語る。
○付き合ってる彼氏が飲食店勤務
○どんな人を結婚相手に選ぼうか迷ってる女性
目次 クリックで非表示→
飲食店勤務の夫を持つ女性の「不安・ストレス・苦労」5選!
飲食店勤務の男性を結婚相手に選んだ女性の「不安・ストレス・苦労」は主に下記の5つだ。
①旦那の帰宅時間が遅く孤独を感じやすい
②休みが少ないので、一緒にいる時間も少ない
③帰りが遅く、会話する時間やお出かけの計画が立てにくい
④子育てに参加してもらえずイライラ
⑤低収入なので経済的に豊かになれない
①旦那の帰宅時間が遅く孤独を感じやすい

パートナーと付き合いが長い場合はもう知ってると思うが、飲食店の社員の拘束時間および勤務時間は異常なほど長時間だ。
◯1日14時間拘束
◯休日が週に1回
◯有給休暇が好きなタイミングで使用できない
◯代わりの従業員がいないので育児休暇が取得出来ない
◯休日でもお店でトラブルがあると出勤する
きっとあなたのパートナーも上記に該当するのでは?
同棲したとしても、仕事の日は出勤前の早朝か、帰宅後の深夜1時すぎくらいしかまともに顔を合わせることが出来ない。それに加えて、休みが少ないと、デートやお出かけに行く時間どころか、会話すら出来ない。
「仕事だから仕方ない…」
現時点でそう思えたとしても、結婚した場合この先ずっと今の状態が続く。子供が出来た場合、育児に協力してもらう時間も体力もないだろう。
②休みが少ないので、一緒にいる時間も少ない

休みが少なければ一緒に過ごす時間なんてない。
一番厳しいのが、「彼は飲食店勤務、私は土日祝日休みのOL」というケース。というのも、飲食店を始めとするサービス業で土日祝日に休みを取ること自体が無理ゲーに近いからだ。
シフトを管理している側(店長やシェフなど)になれば、人員が足りてれば好き勝手休みを入れることは可能だろう。しかし、飲食店勤務の人独特の思考があり、それは、立場が偉くなればなるほど、「土日みたいな忙しい日に休んでられない…」といった謎の正義感が邪魔をし、休める日がどんどん少なくなることだ。
③帰りが遅く、会話する時間やお出かけの計画が立てにくい
■帰宅時間が遅く一緒に住んだとしてもまともに会話する時間すらない
■休みが少なくデートやお出かけする機会がかなり少ない
■そもそも、二人の時間が取りにくい
上記だと飲食店に限らず、他業種・他職種でも当てはまるだろう。
しかし、飲食店は、独特の嫌らしさや悪い伝統がたくさん詰まっており、それを見事に継承してしまう負のスパイラルが未だに存在する。

- 具体的に
■休みを返上し、長時間働くことを美徳としている
■自分のことなど後回し、会社とお客さんが最優先
今の若い世代の人からすれば「ヤバいなこの考え方、古すぎw」と感じるのが当たり前だろう。でも、飲食の世界ではこのような古い考えが未だに存在し続けている。
大昔だと飲食業界に限らずどこもハードワークが美徳とされてきた。しかし、時代は変わり、仕事よりもプライベートや個人に重きを置くことを「理想な生き方」としている昨今、ブラック企業や飲食店の古い考え方は徐々に淘汰されてきている。
しかし、古い考え方が未だに染み付いているのが飲食店だ。アナログな商売だから考え方も古いまま。
働き始めた若手も、最初は「異常だ!やばすぎ!」と感じるが、長く働いていると自然とこの古い考えを受け継いでしまうもの。
長時間労働の繰り返しによって冷静な思考と判断力を失うからだ。
話が大きく逸れそうなので、「負のスパイラル」についての話は省略する。
飲食店勤務の人、つまりあなたのパートナーはいつも下記のようなことをしていると思う。
■もともと決まってた休みの日でも、何か問題が発生したら迷うことなく出勤する(休日返上)
■奥さんや子供、そして自分のことさえ後回しにし、仕事を最優先にする
こんなこと毎回されていては、二人でデートしたり、会話を楽しむなど出来るわけがない。
「好き」・「ずっと一緒にいたい」という気持ちで結婚したはずが、皮肉なことにそんな想いは裏切られ続ける。
「一緒に過ごせる時間が少ないからこそ無理やり結婚した」とも考えらるが、これ、本当に「幸せ」に近づけてるのか?
④子育てに参加してもらえずイライラ

最近では「育児パパ」などという言葉があるように、お父さんも子育てやその他の家事を一緒にやるのが理想とする考え方が広まっている。
だが、もう話の流れからして予想出来ると思うが、プライベートの時間が少ない飲食店勤務の旦那さんは、子育てに参加するのは厳しい。人手不足の現場に勤務している場合、入学式や授業参観などの子供の行事にすら参加することは不可能。
「みんなのパパは来てるのに、ぼくのパパはなんで来てくれないの?」
そう子供に言われたお母さんの気持ちを考えると張り裂けそうなくらい胸が痛む。
⑤低収入なので経済的に豊かになれない
飲食店の正社員は年収が低い。
下記の業種別ランキングを見てほしい。
業種別平均年収データ(2022年9月~2023年8月)

【引用:https://doda.jp/guide/heikin/gyousyu/ 2022年9月~2023年8月の1年間にdodaサービス】
見ての通り、最下位だ。賞与(ボーナス)も最下位。
業種別2021年のボーナス平均額データ

【引用:https://roudou-pro.com/columns/153/ 2021年のボーナス平均額を年代・男女・業種別に徹底解剖!】
飲食の社員の募集には、
「入社すぐに店長就任!月給35万円!」
という文言が記載されている。
案外良い待遇にみえるかもしれないが、飲食店の社員の構造上、年々昇給や、成果を出せば上がることはない。
最初こそ高水準かもしれないが、数年後、他業種に就職した同世代の人に確実に抜かれる。
ベテランになり、結婚して子供が出来たりしても、一年目と変わらぬ給料…。生活が苦しくなり他業種に転職する人やダブルワークする飲食店社員を何人も見てきた。俺もそのうちの一人。
飲食でも大手企業の経営陣クラスになれば年収1000万円稼ぐひともいるが、ごくわずかだし、そこまで上り詰められる覚悟と精神力がある人のほうが少ない。多くの人は並かそれ以下の飲食店員止まりだろう。
一番伝えたいこと

飲食店勤務の男と結婚したら、想像以上に苦労・寂しい思いをします
今回の内容を振り返るとすればこの一言だ。
「知らない方が幸せだった」とか「見なきゃ良かった」など思うかも知れないが、本当にそうだろうか?不満やストレス、孤独を抱えたまま何年も過ごすのと、真実を知り、改めて関わる人を変えたり、理解した上でこの先ずっと一緒になる「覚悟」を決めるのでは「後悔」の大きさが変わってくるだろう。
今まさに旦那が飲食店勤務で夫婦生活に嫌気がさしてるお母さん、これをこの先もずっと耐えれるか?
苦しいけど「好き」という想いは消せないで余計に悩んでたりしてないだろうか?
100%全員というわけではないが、他の職種に比べて飲食店勤務というのは圧倒的にプライベートの時間を取りにくい。15年以上飲食業界を何社も渡り歩いた俺も経験した。
一度本音をぶつけてみることをオススメする。仕事が忙しすぎて普段気が付かなかった「大切なもの」を思い出すきっかけを作れる可能性わずかに残っているはずだから。
家庭やプライベートを軽視する旦那にうんざり!解決策は?

仕事ばかりなのはウンザリだけど分かれたくないし、今後も一緒にいたい
このような悩みに対しての対策はあるのか?
選択肢は下記の3つになる。
①覚悟を決めて乗り切る
②パートナーに転職を勧める
③キッパリと別れる
覚悟を決めて乗り切る

■働き詰めの旦那に気を使って、やりたいことや趣味を自粛
■子供はもちろん、家族揃って晩御飯を食べれない
■「仕事だから仕方ないだろ」と言われると何も言い返せない
今後も不安や孤独と向き合う覚悟があれば、パートナーと今の関係を末永く続けることは可能だろう。
諦めに似た感情だが、
もともとこういう人だから仕方ない
こういう腹を立てないマインドが大切なのかもしれない。
パートナーに転職を勧める

飲食店勤務の旦那さんを持つお母さんの9割はこう思っている。だが、働いている本人(夫)は根っから家庭が嫌なわけでも子供が嫌いなわけではない。
ただ単に時間と気力がないだけだ。
その原因は飲食業界のおかしな労働環境にあるとはっきり断言出来る。
■仕事がキツそう
■育児や家庭云々ではなく、本人がそろそろ限界に近い
■もっと自分と子供のことを考えて欲しい
上記のようなことを思っている場合。自分が抱えてる悩みと、今の生活を続けることのデメリットを夫に打ち明け、飲食業界以外の道へ転職を検討させるのも一つの手だ。
いくらブラック企業が生きにくい現代でも、飲食業界の体質や文化は今後も変わることはない。職場によって差はあるが、基本的に飲食で働く場合は大幅な労働環境の改善は見込めない。
旦那さんがもし、自分でもそのことを理解している場合なら、ブラック飲食業を抜け出す勇気づけになるかもしれない。その決心をした場合、誰よりもそばにいて応援してあげてほしい。
キッパリと別れる
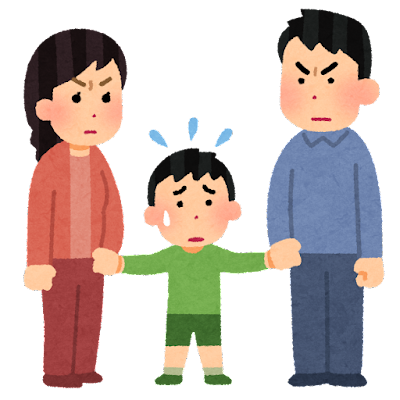

こういう場合は「別れ」を選択するのもムリはない。
「仕事だから仕方ないだろ?」
「みんな苦労してんだよ!」
こんな言葉はうんざりだ。幸せになるために結婚したのに、なんでお互いの時間が共有出来ない生活を続けるのか?フラストレーションが溜まっていくばかりの生活を我慢して、夫婦も子供も幸せになれるのか?
この生活をあと何十年耐え続けないとダメなんだ?
「結婚」した意味がない。
まとめ
○それを理解した上で結婚する、別れるなどを検討するのが大事
○お互いの価値観を共有し、転職を勧めるのも一つの手段
【関連記事】
30代向け
なぜ30歳を過ぎた私でも未経験・ホワイト企業の正社員に転職できたのか?
20代向け
本気で転職したい20代飲食店勤務のあなたへ!忙しくても1ヶ月で内定を貰える方法とは?
ホワイトな飲食店を探している方向け
飲食店はどこもブラックでしょ?しかし、このサイトを見た瞬間…!
今すぐにでも飲食店辞めたい人向け
バックレはするな!こうして私は会社にいかずにブラックな職場を退職しました